鍼灸のイメージって?
皆さんは鍼灸にどんなイメージをお持ちでしょうか?昔はやった韓流ドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』『ホジュン~伝説の神医~』なんかの治療シーンに出てきたマッチ棒みたいな鍼を刺すシーンを思いうかべるかもしれませんね。インスタなんかに流れる流行りの美容鍼動画なんかでよく見る顔中に鍼を刺して何十本~何百本とぶら下げた写真なんかを思いだすかもしれませんね。こうやってたずねると絵的に印象に強く残るインパクトの強いイメージばかりが出てきますが、実はそれらは極端な例です。
強いイメージとは反対の鍼灸もあるよ
もちろん、それらも鍼灸です。けれども、もっと地味な鍼灸もいっぱいあります。すごく細い鍼で刺してるのがわからなくなる位まで刺激を弱くしたものや、1本1本の効果を上げて出来るだけ本数が少なくなるように工夫したりしたものもあります。見た目インパクトばかりに目がいくと鍼灸の本質的な部分が見逃されてしまいます。
鍼灸を一般論で…
強いインパクト的な部分を外して、あえて皆さんのイメージを集約していくとどんな感じになるでしょうか?こんな感じのまとめが出来あがるのではないでしょうか?
金属を細くして尖らせた鍼というものを謎のツボ(経穴)というポイントに刺しこんで痛みや苦痛を取る方法
モグサという綿ホコリみたいなものを肌にのせて火をつけて温めて体調改善をはかる方法
もう少しそれっぽく言えば
鍼や灸という特別な道具をツボという特別なポイントに刺したり温めたりして健康や症状を改善する医療系の技術
みたいな言葉でまとめられるのではないでしょうか?
どうでしょう?
「うん、そんな感じだと思ってた」
となるのでしょうか?
…なったとして話を先に進めます。
一般的なイメージに鍼灸師が足りない部分を補ってみる
上記のまとめが間違っているわけではありませんが、ただ鍼灸師の立場からするとちょっと残念な感じがしてしまいます。長所?というか他の道具や治療法と違う特徴的な部分が見過ごされてしまっているように思えます。その辺りを補足してみたいと思います
①鍼の尖端は作りがとても精工なので縫い針や注射針と違う感覚が起こる
まず、鍼という道具そのものについてです。鍼と聞くと、裁縫に使う針とか、注射針とかとゴッチャに連想されてる方も多いのではないしょうか?鍼灸に使う鍼はそんなに狂暴ではありません。
日本でよく使われている鍼は太さが0.12~0.34mmくらいです。(髪の毛程の太さからやや太いくらい)また鍼の先は非常に滑らかに尖らせてあり肌をつらぬく際の損傷をピンポイントで最小限に抑えるように設計されています。また鍼の材料である金属には弾力性を持たせてあり、鍼先が痛みを感じやすい皮膚表面を一瞬で通り抜けるように工夫されています。
そういった工夫の結果、普段私達が日常的に感じるような痛みを最小限に抑えて、痛みとは違う種類の刺激を「からだ」に与えることが出来るようになっています。ジワーンとしたとか、ズーンとしたとか、表現されることが多い「響き」と呼ばれる感覚です。(これを痛みと表現して嫌がる人もいますが、逆にこの感覚が好きで「もっと響かせて」と言ってくる人もいます。また自覚されにくいモヤ―ーとした響きの場合は「全然痛くない」と表現される方も多いです。)この特別な刺激が「からだ」の回復力、治癒力、バランス力を呼び起こすのです。
対して、病院等の採血で使われる注射針が0.6~0.8mmくらいです。血液を通すため中空になっています。そのためにはある程度の太さが必要です。なので、鍼灸の鍼より太いのです。また、中空の管なので針先を真っ直ぐ尖らせられません。そのため、尖端は斜めに切った竹槍のような形状をしています。このため傷口が刃物で切ったよう横に拡がってしまいます。どうしても鋭い痛みは発生してしまいます。
当然ながら、衣類を縫う針とは比べるべくもありません。元々ある繊維のスキマに針先を潜り込ませるためだけの尖端なのでそれ程尖らせる必要はありません。また、生地から引っ張り抜くためには針を摘まみやすいようにある程度の太さと硬さ備えている必要があります。なので、マチ針や縫い針で指先を刺してしまった時は強烈に痛むのです。この感じは鍼灸の鍼とは全くかけ離れた感覚です。
②ツボは電気のスイッチみたいなものじゃない
次に気になるのがツボの理解のされ方です。
「ここは肩こりに効くツボだ」とか
「ここに灸を据えれば吐き気がおさまる」
…○○のツボ、××のツボみたいな紹介のされ方をしています。完全な誤解という訳でもないのですが正確さにはとても欠いた表現だとは思います。正確には
「このタイミングでこんな肩こりにはココは効く可能性が他より高いツボだよ」
「こんな時にここにお灸を据えれば吐き気がおさまる可能性が高いよ」
みたいな表現になると思います。なぜなら、ツボは部屋のカベに埋め込まれた照明のスイッチみたいなものではないからです。一つのツボの中に幾つもの繋がり方があります。「からだ」は単純ではありません。同じツボでも、鍼の刺し方やあて方しだいでその後の「カラダ」の反応は変わってきてしまいます。私達鍼灸師はツボとその周囲の様子を観察しながら、このツボのこの辺をこんな風に刺激できればこの症状を抑えられるに可能性が高いよな…みたいに感じながらツボを選んで刺激しているのです。鍼灸師観点から言えば、効きそうなツボをちゃんと選んでその働きを上手く引き出すのが腕の見せ所なのです。つまり、ツボの効果は施術者の「からだ」への理解やテクニックしだいで結果は大きく変わってしまうのです。
③お灸は単に温めているのではない
3つ目はお灸です。お灸は温めて身体を治す方法だと広く思われています。別にそれで間違いではありません。お灸の効果の中には温熱刺激による効果もあります。けれども、温めるだけの効果なら使い捨てカイロや湯タンポの方がしっかり温められます。ではなぜピンボイントで温めるみたいな面倒なことをするのでしょうか?私達鍼灸師の経験をもとに答えれば、【温度差を与えるため】ということになります。お灸を据えるとツボの狭い範囲にだけ短時間ちょっと熱いくらいまで温まります。燃え尽きると熱が逃げて冷えてきます。その上にまたお灸を据えると、再びちょっとだけ熱いくらいまで温まります。この対比、お灸据えてる場所とその周辺、お灸が燃えたり消えたりする…冷→温→冷→…の繰り返しが温度差として「からだ」に与えられます。私達は熱くなっていても熱いことに気付けない状態に、冷えてても冷えていることに気付けない状態にすぐになってしまいます。この“気付けない”状態は「からだ」の調整機能が上手く働いていないということです。温冷の対比を与えることによって、その異常を「からだ」に”気付いて”もらえるように誘導するのです。気が付けば、「からだ」は自ら温める方へ動いていきます。冷えてるから温めてあげる…というより、冷えてることを気付かせて自ら温めることを思い出させるという感じがお灸の特徴なのです。
鍼灸師が描く鍼灸のイメージ
上記のように一般の方と鍼灸師が思い描くそれぞれの鍼灸のイメージの間には少しズレがあるのが想像できたのではないでしょうか?このズレは小さいようでいてかなり大きな差だと私は考えています。なぜなら鍼灸の大切な部分、エッセンスはこの小さく見えるズレの方にあるという風に私には見えているからです。では、その大切な部分、エッセンスは何なのか?私はこう考えています。
鍼灸のエッセンスは「からだ」とのミュニケーションを介した細やかな微調整の方にある
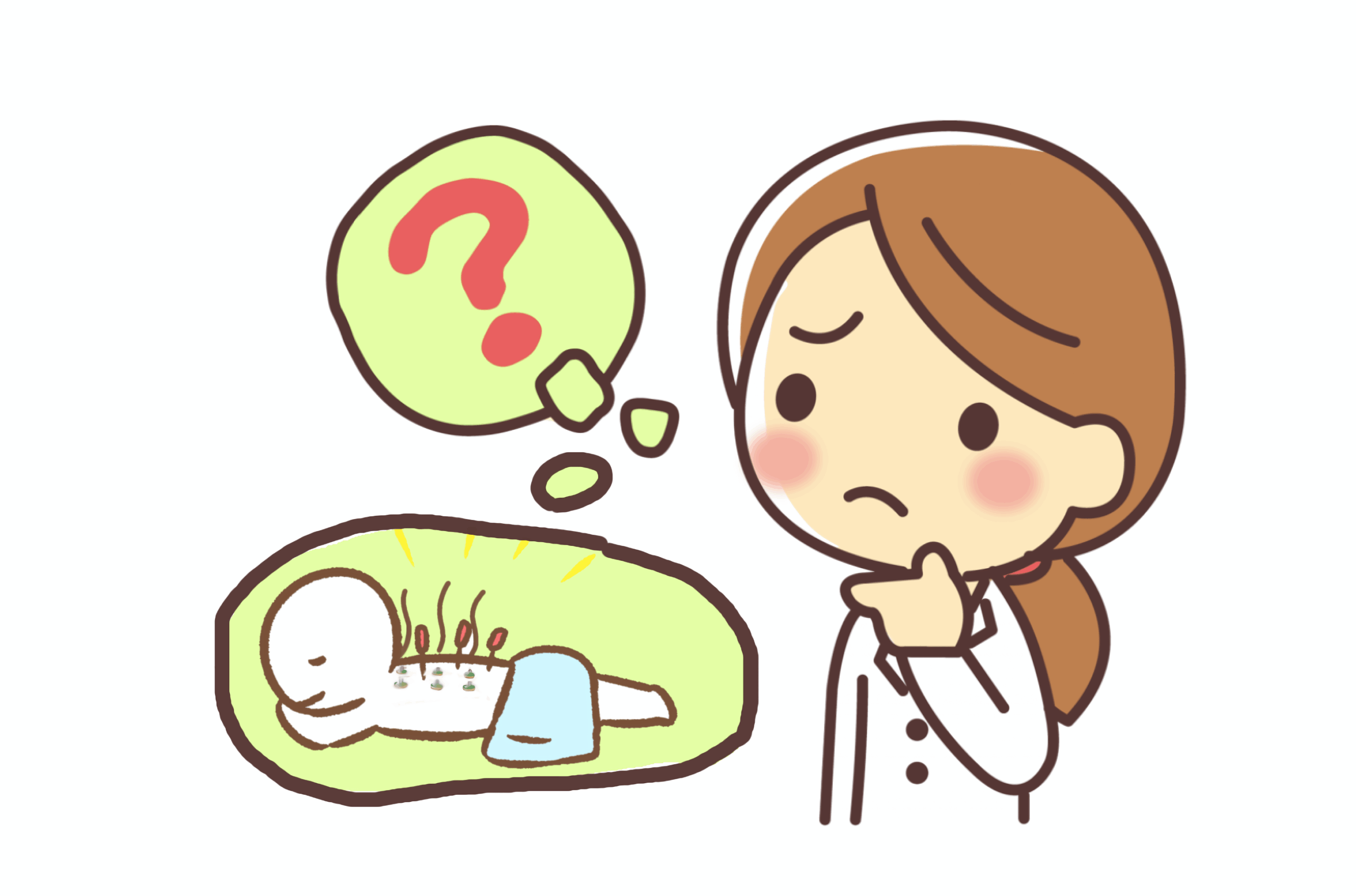
鍼灸の特殊に見える方法はそのコミュニケーションのために工夫されたただの一側面にすぎないのです。当院ではそのエッセンスに忠実でありたいと考えて【 「からだ」の声を聴こう!】というコンセプトを掲げて施術しています。
ご予約/ご相談はコチラから↓
0798-26-9117 に電話をかける
公式LINEでご相談/予約も可
初診のWeb仮予約
口コミやネット情報だけではわからないことが、沢山あると思います‼️気楽にご相談下さい



コメント